【妊娠中のストレス】胎児への影響は?イライラの対処法なども説明
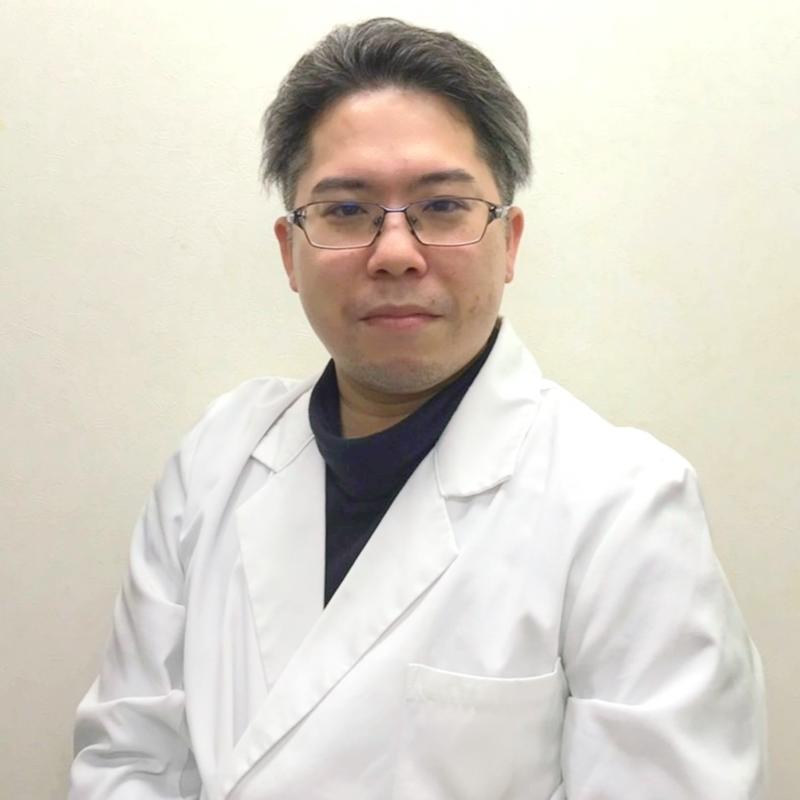
2025.01.28
記事監修
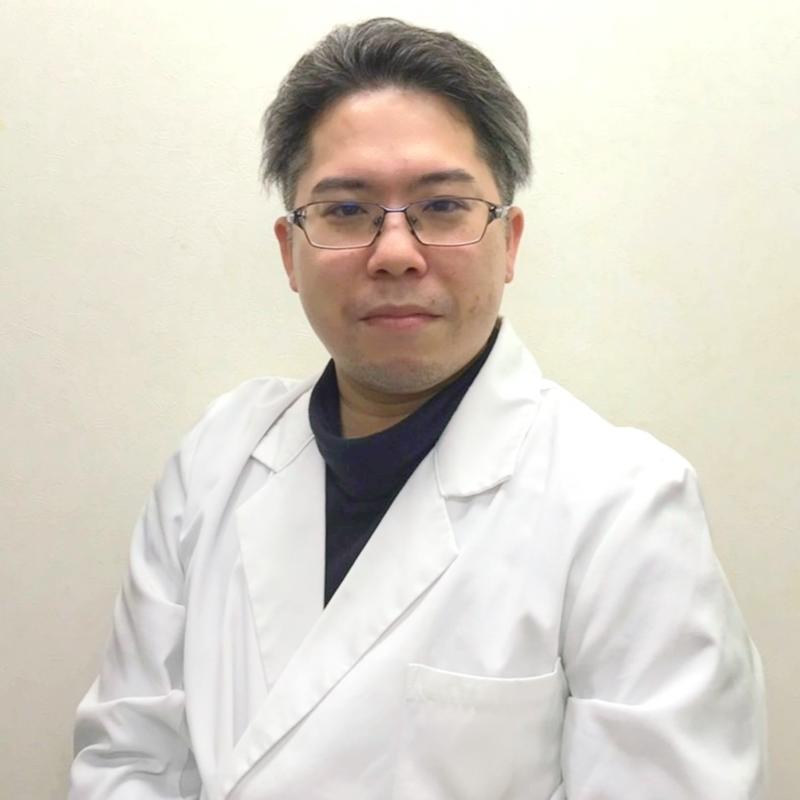
阿部一也先生
日本産科婦人科学会専門医

「妊娠中はいつまで仕事をしていいの?」
「産休はいつから?」
「妊娠初期でも仕事がしんどい、もう休みたいけど甘え …?」
妊娠が発覚すると色々と考えてしまうこともありますが、その中でも仕事のことを気にする方もいるのではないでしょうか。
ここでは妊娠中の仕事について気になる方に向けて、妊娠中の仕事はいつまでして良いのか、妊娠と仕事に関連する法律や、周囲への報告・相談、仕事をすするときの注意点、妊娠発覚時にしておきたい基本的なことについて説明します。
妊娠中の仕事は妊娠8カ月から9カ月までの方、産休に入るまでの方が多いようです。人によっては妊娠3カ月から7カ月でお仕事から離れる方もいるでしょう。
つわりや妊娠により起こる不調の程度は人それぞれです。産休まで働く方もいれば、もっと前に仕事をするのがつらくなる方もいます。妊娠に配慮してくれる職場もありますが、基本的にはご自身で仕事の調整をしていく心づもりで過ごしておく方が良いでしょう。
重い荷物を持つ業務を交代してもらったり、出張が多い職種の方は別の職種に変えてもらったり、職場に相談することで解決することが可能なこともあります。
一方で、数は多くないようですが、マタハラ(マタニティハラスメント)を経験される方もおられるそうです。妊娠をきっかけに解雇や自主退職などの不利益な扱いを受けることは法的に問題でもあるため、もしマタハラにあったら、いざというときに対応できるよう、証拠となるものを集めておきましょう。会社のコンプライアンス部門や社外の労働局にマタハラについて相談することも可能です。

基本的な知識として、ここでは妊娠と仕事に関係する法律や制度について説明します。
ここでは労働基準法や男女雇用機会均等法 、育児・介護休業法、 母性健康管理指導事項連絡カード について確認していきましょう。
労働基準法の中には、妊娠中や産後の女性を守るための職場での規定も定めています。
同法第64条では危険有害業務の就業制限を設けており、重いものを持ったり、有毒ガスなどを発散する場所での就業を禁止したりするといった、妊産婦の体と哺育などに影響を及ぼす業務に就かせてはいけないという決まりがあります。
また、第65条では産前休業は出産予定日の6週間前から、双子以上の妊娠の場合は14週間前から取得可能です。産後は出産の翌日から8週間の休業期間を入れるといった事項にも触れられています。
そして、第67条では育児時間について、生後1年に満たない子を育てている間は1日に2回、それぞれ少なくても30分以上の育児時間を申請することが可能です。
男女雇用機会均等法は、解雇や労働契約、採用、昇進・降格など労働全般において性別を理由とする差別が禁止されています。
妊娠に関連するものとしては、第13条にて妊娠に伴う体調の変化が考慮されており、医師の指導があった場合には勤務時間や仕事量の調整などが可能と定められています。
また、第23条により、通勤ラッシュ時の電車で押されたり転倒したりするリスクがあることから、通勤方法の変更も可能です。
育児・介護休業法は、育児や介護に参加しやすいように事業主が従業員の労働時間に講じるべき措置を定めたものです。
第5条では子どもが1歳になるまで、場合によっては1歳6カ月や2歳になるまで育児休業が可能であることが定められています。
第16条では残業(所定外勤務)の免除と子どもの看護休暇、第17条では時間外労働、第19条は深夜勤務について、第23条では育児のための時短勤務について記載されているので、確認しておきましょう。
母性健康管理指導事項連絡カードは、妊婦さんに必要な措置について、医師が妊婦さんを経由して事業主に連絡するためのカードです。母健カードや母性カードとも呼ばれています。
医師から事業主に対しての連絡であるため、カードを活用することで職場や仕事内容に関する調整を相談しやすくなるでしょう。
厚生労働省のホームページにPDFのフォームが公開されているので、必要な場合は印刷することをおすすめします。また母子健康手帳にもカードの見本が ありますので、確認してみましょう。

妊娠をすると周囲への報告について気になる方も多いのではないでしょうか。
報告や相談に関しては、育休などと異なり、特にルールを定めていないので、報告や相談について気になるかと思います。ここでは職場だけでなく、家族に報告する場合や、妊娠中にお仕事を変えたときについても触れておきます。
人事部や上司に対しては、妊娠がわかった時点で伝えておくと良いでしょう。理由としては、妊娠による急な体調不調で、予定通りに出勤できなくなる可能性があるからです。報告する際に躊躇される方もいるかと思いますが、早めに引き継ぎの業務や体制を整えておいた方が良いと言えるでしょう。
業務的に直接影響がない方や同僚への報告は、人間関係に配慮しつつ伝える形で差し支えないでしょう。そのため、安定期に入ってから伝える妊婦さんもおられます。
また、産休復帰後に気持ちよく仕事を開始できるよう、産休前の最終出勤日などは、マナーをわきまえて社内や社外に挨拶しておきましょう。
パートナーの方には、産婦人科で妊娠と診断されてから伝える妊婦さん、または、早い方であれば妊娠検査薬で陽性が確認できてすぐに伝える妊婦さんが多いかと思います。
妊娠検査薬の結果が陽性であれば妊娠している確率は高いですが、妊娠初期に流産となる可能性もあります。慎重に進めたい方は医師による確定診断が出た後に報告や相談をするとよいでしょう。
家族への報告は、パートナーへの報告と同時にするか、安定期に入ってから伝えるかは個人によって異なります。負担を感じないタイミングで共有しましょう。
妊娠中に働く場合はパートナーや他の家族のサポートや理解が欠かせません。送迎が必要なときやドクターストップがかかって急に働けなくなることもあるので、妊娠中に働き続けるかどうかは家庭内で事前によく話し合っておきましょう。
妊娠中に仕事を探す方は、前提としてパートナーや医師に相談したうえで仕事探しをしましょう。働きたい気持ちが強くても、家庭的にも身体的にも問題はないか確認しておく必要があります。
また、応募先の企業には、事前に妊娠中であることを必ず伝えましょう。伝えておかないと妊婦さんにとってはハードな業務を任されたり、想定外の体調不良などが起こって信頼関係を築けなかったりする懸念点があります。
産休を意識して、いつまで働くつもりでいつ復帰する予定かも相談できると、応募先も適切な判断をしやすいでしょう。
産後に復帰しやすい職種には、医療事務や介護職などが挙げられます。妊娠中は移動中に急な体調の変化が起こることも想定されるため、家から近い場所を選ぶことも大切です。
ここからは、実際に妊娠中に仕事をすするときの注意点について紹介します。
体への負担や危険が大きくならないように、また、いつでもかかりつけの病院で診てもらえるように準備しておくことが大切です。
特に今までハードな仕事をこなしてきた方は妊娠中に働き過ぎないように注意しましょう。体の負担が増えると、性器出血や腹痛の原因につながる可能性もあります。
家族や職場、周囲の方々からのサポートを受けつつ、無理のない範囲で働く意識が大切です。体調に波があって仕方がない時期なので、仕事において自身を責める必要はありません。ご自身の体調と赤ちゃんのことを第一に考えて、必要な時には業務の見直しなどもして過ごしてくださいね。
慢性的な疲労や仕事で感じるストレスは、自分では自覚がないままにためやすいため注意しておきましょう。
妊娠時にはつわりによって吐き気や頭痛、胃の不快感など、さまざまなトラブルが発生しやすく、疲労やストレスもためやすい時期 です。さらに、疲労やストレスが体への負担につながるため注意が必要です。
睡眠をしっかり取り、疲れたときには好きな音楽や映画を楽しんだり、友達としゃべったりしてリフレッシュすることをおすすめします。

ラッシュ時の電車は他人との接触が避けられない場合があります。車内で押し潰されたり、転倒したりする危険もあるでしょう。通勤時間をずらすか、通勤手段の変更をパートナーや職場に相談する、リモート勤務に切り替えることなどを検討するといった、心身ともに安全な対策をしておくことをおすすめします。
どのような業務を避けるべきかは、職場によって異なりますが、転倒やけが、重いものを扱う業務は避けておきましょう。先述の労働基準法においてもお伝えしましたが、事業主は妊娠中の方が危険な業務をしないようにすべきと定めています。
妊娠中はつわりや貧血を起こしやすいため、多少の体調不良であれば「大丈夫かも」と思う方もおられるかもしれません。
とはいえ、体調不良の原因が妊娠性糖尿病や妊娠高血圧症候群など、無視できない症状によるものである可能性もあります。妊娠糖尿病 は胎盤から分泌されるホルモンにより体内の糖代謝がうまくできず 、お母さんも赤ちゃんも高血糖の状態になるものです。具体的には網膜症や腎症、羊水量の異常、流産、巨大児の出産につながる場合があるでしょう。
また、妊娠高血圧症候群は妊娠20週以降に高血圧を初めて発症 することです。妊娠前もしくは妊娠20週までに高血圧を呈している場合は、高血圧合併妊娠と呼ばれていますが、こちらも妊娠高血圧症候群の範疇となります。
妊娠高血圧症候群 が重症化すると、肝臓や腎臓機能の障害、子癇(しかん)発作、胎児の発育不全、常位胎盤早期剥離など危険な状態に陥ることがあります。
体の異変を感じ、性器出血や腹痛などの症状があっても、中には我慢してしまったり、大丈夫だろうとそのままにしてしまったりする方がおります。これは非常に危険なことでもあり、必ず普段の妊婦健診や、異変を感じたらかかりつけ医に診てもらい、ご自身と赤ちゃんの状態をきちんと管理しておくことが大切です。
妊娠できてうれしい気持ちや仕事のことを考える一方で、「具体的にどんなことをしていくべき?」と気になるお母さんもいるのではないでしょうか。
最後に、妊娠が発覚した時にしておきたいことについても確認しておきましょう。

妊娠に関係する社会制度は多くあるため、お住まいの地域で受けられるサポートや勤務先の企業の規定などを改めて確認しておきましょう。
自治体によっては、保育園や幼稚園などとは別の場所で産後にお子さんを預けることができる場所が用意されていたり、お子さんの送迎をサポートしてもらえたりすることもあるようです。
また、育児を開始してから受け取りが可能となる育児休業給付金(育休手当) の場合、勤務日数を変えずに時短勤務を選ぶと受取額が減少した事例もあります。
言い換えると、時短勤務ではなく勤務日数を減らした場合の方が受取額が多くなる、と計算できる場合もあるようです。受給額の計算など、複雑に感じることもあるかと思いますが、ご自身の場合だといくらなのかシミュレーションしておくことが大切です。
体調や状況によって、どのような働き方が最適かは断言できない部分ですが、できる限り理解しておくことをおすすめします。
体調面では飲酒や喫煙をやめること、睡眠や食事などの生活習慣を整えること、カフェインの多量摂取や、自己判断によるお薬の服用を控えることが大切です。
産婦人科にて「妊娠」と診断された後は、妊婦検診費や出産育児一時金などにおいてサポートを受けられるよう、自治体に妊娠届出書を出して、母子健康手帳を受け取りましょう。
働く妊婦さんは労働基準法や男女雇用機会均等法などの法律によって守られています。仕事の引き継ぎなどが生じるため、上司や人事の方には早めに相談しておくと安心かと思います。
妊娠後期や産休前まで働く方も多いですが、妊娠による体調の変化は個人差が大きいため、ご自身の体調を考慮しつつ、スケジュールを決めましょう。
パートナーや家族、職場の人、自治体のサポートなどを頼りつつ、元気な赤ちゃんを迎える準備をしてくださいね。
記事監修
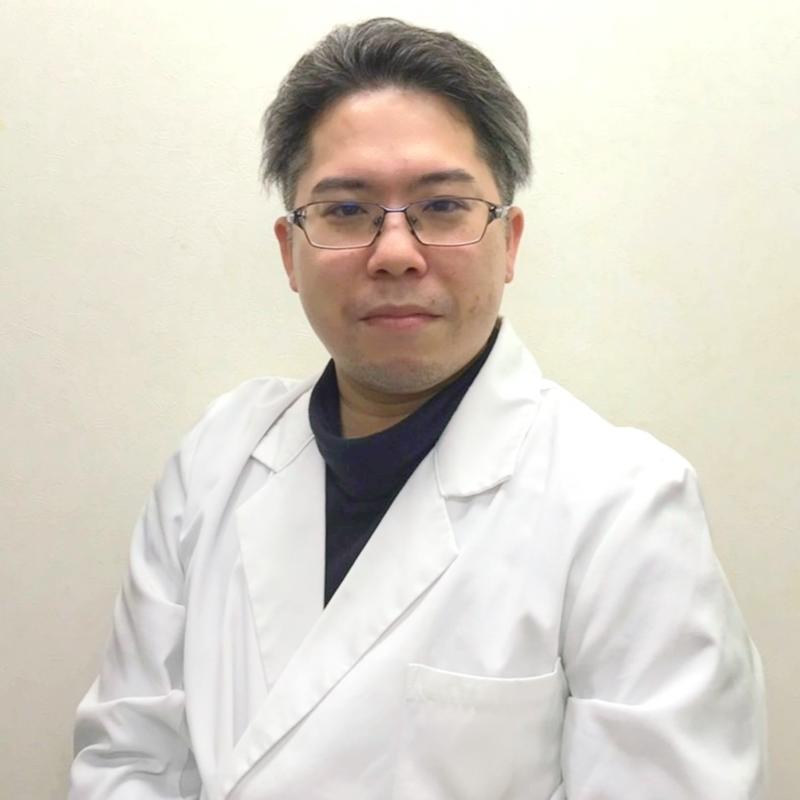
阿部一也先生
日本産科婦人科学会専門医
プロフィール
2009年東京慈恵会医科大学医学部医学科卒業。2009年板橋中央総合病院初期研修医。2011年同院産婦人科入局。日本産科婦人科学会専門医として、妊婦健診はもちろんのこと、分娩や産まれたばかりの新生児、切迫流早産の管理などにも対応。産婦人科領域においての不安、心配や疑問に的確にアドバイスできるよう、記事の監修や執筆にもあたっている。
関連記事
おすすめの監修記事